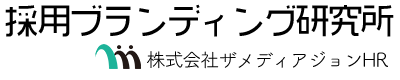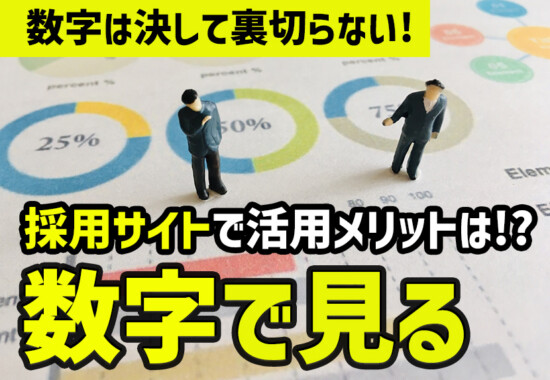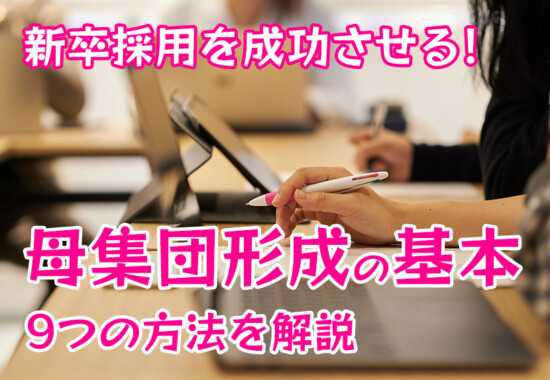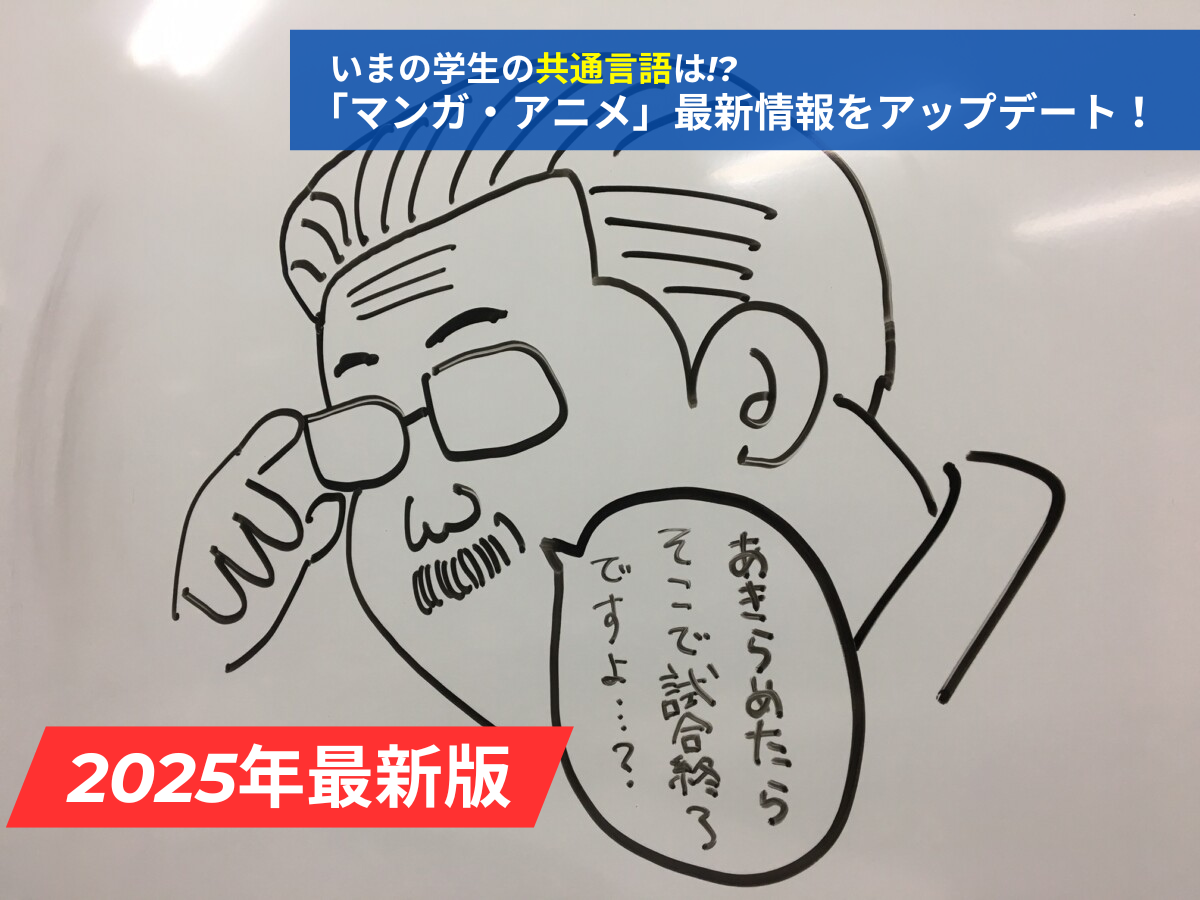
【採用担当者向け】「あきらめたら、そこで試合終了だよ」はもはやNG!? 学生の心をつかむための最新の”共通言語”はコレだ!<2025年最新版>
「最近、学生とどうも会話が盛り上がらない。距離感をどう縮めればいいのかわからない・・・」
そんなお悩みを抱える、経験豊富な人事・採用担当者の方へ。
過去にも学生と距離を縮められるマンガについてを記事にしましたが、時代は進み、そのマンガ・アニメも変化しています。
学生との距離をグッと縮め、フランクな雰囲気を作り出すための「共通の話題」、特に彼らの文化の核にある「マンガ・アニメ」の最新情報をアップデートしましょう。
① 昔の名作は「古典」として扱いましょう
かつては絶大な効力を持っていた名言や作品も、今の学生に話す際には「古典」として扱うのが得策です。
【もはや「共通言語」ではない名言たち】
・「あきらめたらそこで試合終了だよ」(『SLAM DUNK』安西先生)
・「左手はそえるだけ」(『SLAM DUNK』)
・「クリリンのことかーっ!!!!」(『ドラゴンボール』)
これらのフレーズは、30代・40代にとっての「仕事の壁にぶつかった時の激励」であり、「共通のノスタルジー」でした。しかし、今の学生世代にとっては、「親や先生が昔見ていた名作」という認識です。
・知っている率: ほとんどの学生が作品名は知っています。
・共感度: 具体的な名シーンや文脈まで理解している学生は少数派です。
「このセリフの良さを共有することで距離を縮める」という意図で使うと、「ぽかーん…」とされるか、「おじさんの昔語り」として流されてしまうリスクがあります。これらの作品は、学生が興味を示した場合の「古典」として話す程度に留めておきましょう。
② 現在の学生の「共通言語」マップ【2025年最新版】
学生との距離を効果的に縮めるには、彼らの青春時代に熱狂的に流行した作品、または現在進行形で話題になっている作品を使うのが最も効果的です。
(1) 不動の「レジェンド」作品
長年にわたり人気を誇り、「人生の教訓」を語りやすい作品です。
【作品名/理由と採用での活用例】
●『ONE PIECE』
世代問わず「人生のバイブル」。ルフィの生き方や仲間の絆は、内定者研修や組織論に絡めても使いやすい普遍的なテーマです。
●『NARUTO -ナルト-』
海外人気も高く、共感度が高い。努力、孤独、友情のテーマは深く、担当者が全巻読破した経験を話すと親近感が生まれます。
(2) 今の学生の「ど真ん中」を捉える作品
この数年で社会現象を巻き起こし、学生がSNSや友人との会話で使っている「共通語」と考えられる作品例はこちらです。
【作品名/特徴と採用での活用ポイント】
●『呪術廻戦』
2018年〜連載開始。今の学生の「ど真ん中」。ダークな世界観と能力バトルが人気。「推しのキャラクター」や「あのシーンの解釈」など、カジュアルな話題に最適。
●『ハイキュー!!』
スポーツマンガの最高傑作の一つ。戦略的な描写が現代の学生に刺さる。2024年劇場版も大ヒット。チームワークや努力のプロセス、役割分担について語る際に非常に有効。
●『進撃の巨人』
完結済みですが、社会性、倫理、リーダーシップなど深いテーマを持つため、議論のきっかけに最適。「仕事で壁にぶつかった時」の例え話として、リアリティをもって使える。
●『僕のヒーローアカデミア』
「個性(能力)」と「努力」がテーマ。「自分の強み(個性)を仕事でどう活かしたい?」という話題に繋げやすい。
●『SPY×FAMILY』
家族の絆、コミカルさ、シリアスさが融合し、アニメも大ヒット。男女問わず人気があり、ライト層にも通じやすい。
●『ブルーロック』
新しいサッカー観・エゴイズムがテーマ。徹底的な成果主義や競争を求める職種の話題に絡めると、熱い議論になる可能性があります。
●『薬屋のひとりごと』
異色の後宮ミステリー。知的好奇心や論理的思考力を持つ主人公の物語。「分析力」や「問題解決能力」を重視する職種の話に絡めやすい。
●『怪獣8号』
ジャンプ+発の人気作。「年齢を重ねてからの再挑戦」がテーマ。既存のキャリアに縛られない、新しい挑戦を奨励する際に共感を得やすい。
③ マンガを共通言語にするための具体的なテクニック
共通の話題を持つことは、学生に「この人は話が通じる」「気軽に話せる人だ」と思わせるための強力なツールです。
(1) 知識の「深さ」よりも「歩み寄る姿勢」を重視
長々と昔のマンガの知識を披露する必要はありません。重要なのは、「あなたが今の学生の文化に歩み寄ろうとしている姿勢」です。
NG例: 「俺はスラムダンクをリアルタイムで読んでいてさ…」
OK例: 「『ハイキュー!!』の映画がすごい人気だったみたいだけど、一番好きなキャラクターは誰?」
より良いOK例: 「私も『薬屋のひとりごと』を少し読んでみたんだけど、主人公の猫猫のどんなところが面白い?」
(2) 「推し」を聞くのが最短ルート
キャラクターの「推し」は、学生の価値観を最も表しています。
「どうしてそのキャラが好きなの?」と聞くことで、その学生が仕事で何を重視するか(努力、才能、合理性、優しさなど)を知るヒントになります。
(3) 自分の「過去の推し」をカミングアウト
昔のマンガの話をするなら、自分の趣味を打ち明ける「自己開示」のツールとして使いましょう。「『呪術廻戦』もいいけど、実は私は『めぞん一刻』にハマっててね…」といった話題は、あなたの「人間らしさ」を伝え、学生の警戒心を解くことに繋がります。
採用活動において、テクニックやロジック以上に「距離感」は大切です。学生が心を開くための鍵として、ぜひ最新の共通言語を取り入れてみてください。